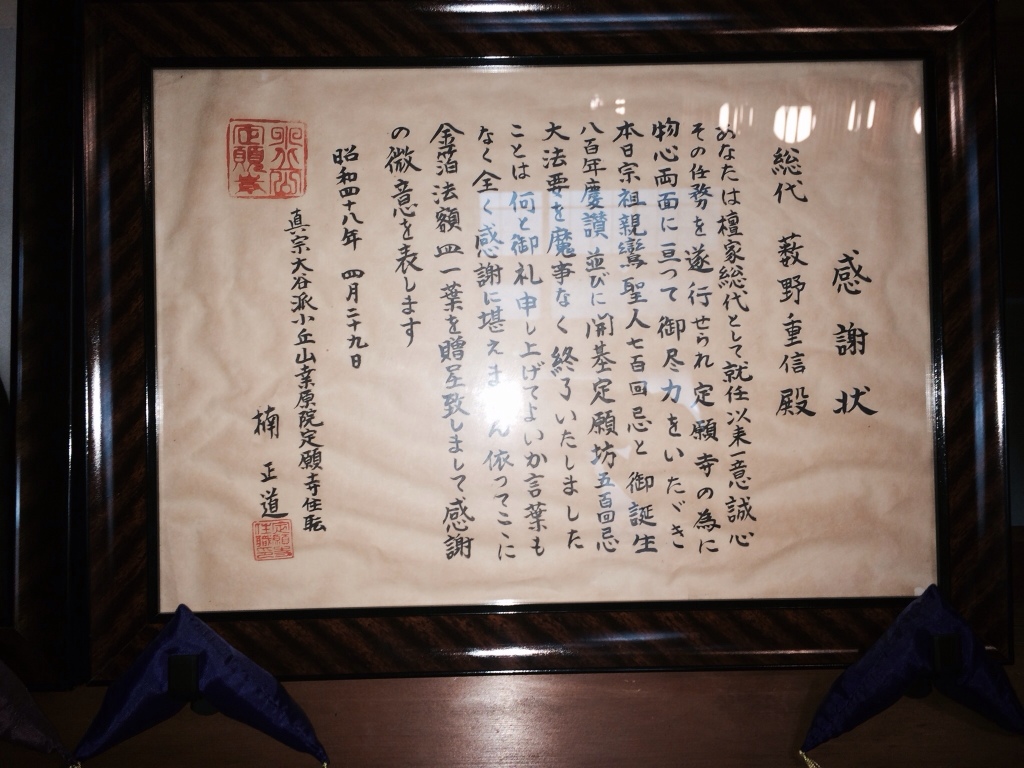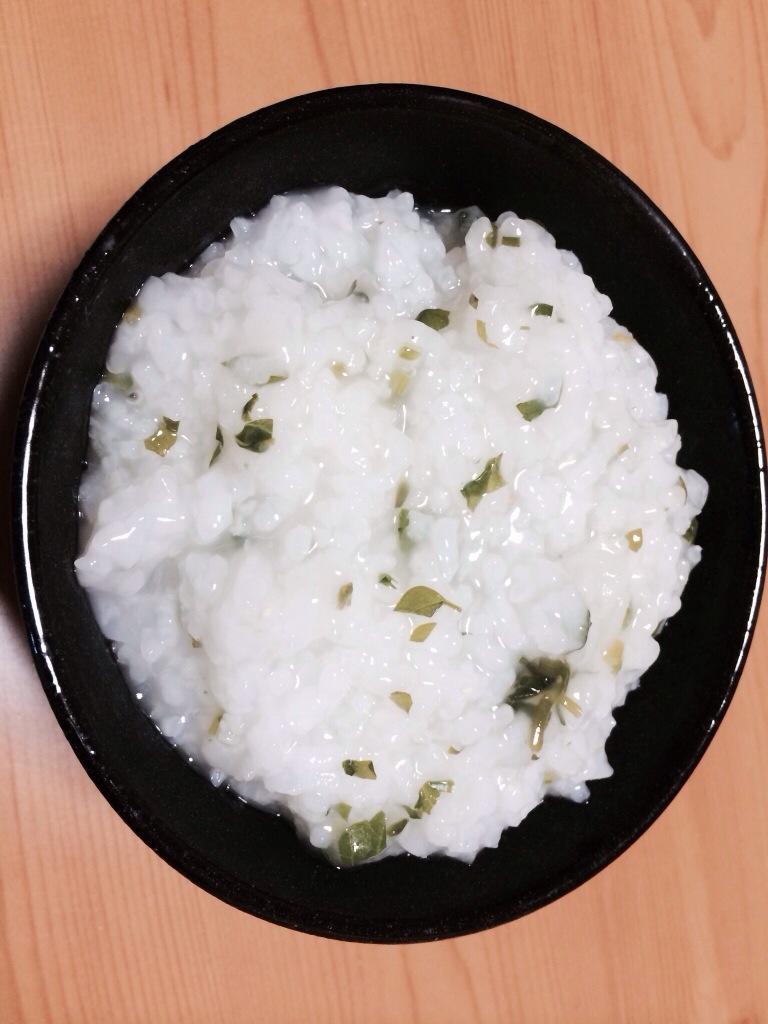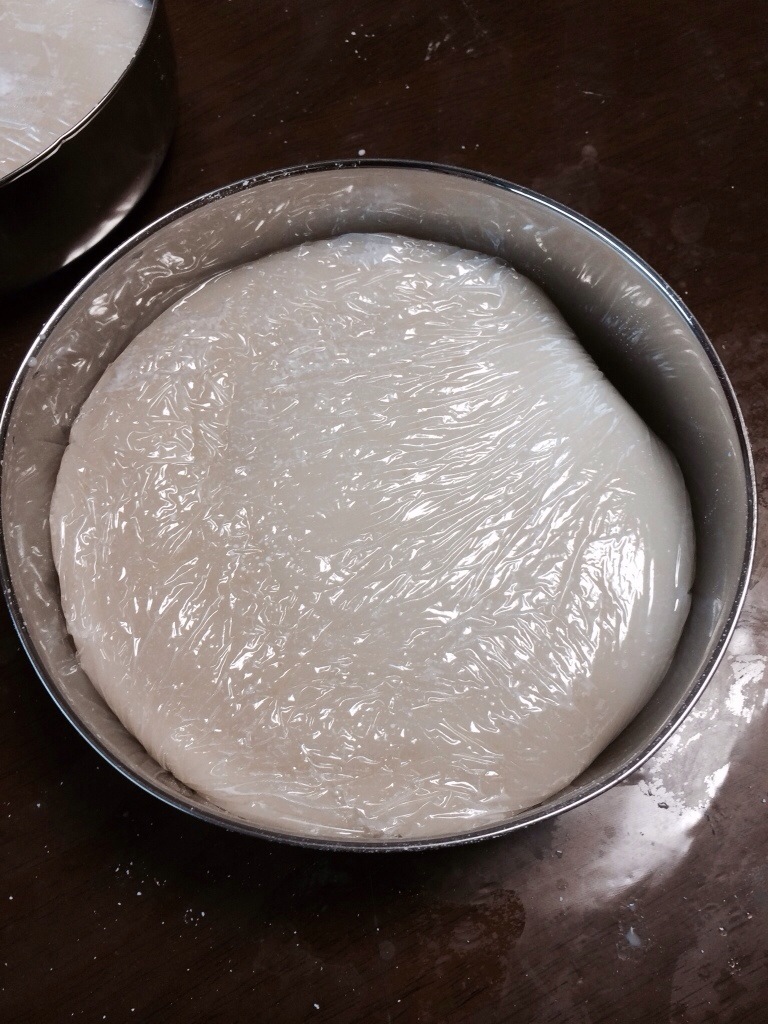2014年の幕開けとなる修正会法要が勤まりました。

午後より1冊の本を読みました。あるジャーナリストの方が書いた仏教の入門書のような本でした。
本の中にインドの話が出てきますが、今日はこの本を読みながらこんなことを思い返していました。私自身、大谷大学短期仏教科の時に研修でインドに行ったことがあるのですが、釈尊の史跡なども載っていて当時研修した場所の1つブッダガヤが、紹介されていました。

これは若院がその研修の時に撮影したブッダガヤの大菩提寺の写真です。当時はこのように修復作業中でした。

こちらは仏塔の内部の釈迦牟尼世尊です。この写真も同じく研修の時に撮影した物です。
ブッダガヤはもう皆様もご存じの通り、釈尊が悟りを開いた場所であり、現在は世界遺産になっているようです。
親鸞聖人は
如来所以興出世 唯説弥陀本願海
【読み方】
如来〈にょらい〉、世に興出〈こうしゅつ〉したまうゆえは、
ただ弥陀〈みだ〉本願海〈ほんがんかい〉を説かんとなり。
と正信偈に書かれていますが、釈尊が、この世間にお出ましになられた目的は、ただただ、阿弥陀仏の海のように広大な大悲の本願のことをお説きになるためであった、ということでありますが、すべての原点はこのブッダガヤからはじまっていると言っていいのではないでしょうか。
またブッダガヤには大きなハス池がありますが、

ブッダガヤのハス池〈写真は適当な写真が古ぼけていてためネットより拝借)は釈尊が沐浴されたとされていますが、当時私はこのコブラの中に座っている釈尊に向かい「ブッダンサラナンガッチャミー」と唱えた時に国籍を超えて大合唱したことを思い出しました。意味も無くなぜか涙をながして感激したことを今でもはっきり覚えています。釈尊が悟りを開いた場所は15年も前に研修した場所ですが又行ってみたいと思いました。
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi (ブッダンサラナンガッチャーミー)
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi (ダンマンサラナンガッチャミー)
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi (サンガンサラナンガッチャミー)
(パーリー文といって私は仏に帰依します。私は法に帰依します。私は僧に帰依しますといった三帰依の意味)
歌にもなっているのですが、自分が子どもの頃、先代住職がよく歌っていたのを思い出しました(笑)
いつの日か定願寺からインド旅行に行く日があればいいな・・・・・と思いました。
合掌